研究室から危険なウイルスが外部に漏れた
研究室から危険なウイルスが外部に漏れた!
| 今月の相談 | 研究室から危険なウイルスが外部に漏れて人間に感染してしまいました。また、それを取り扱っていた研究者も感染してしまいました。このような場合、どうすればよいでしょうか? |
|---|
危険なウイルスを取り扱う場合
日常の社会生活のなかでは、人間にとって危険なウイルスを保管、管理することは、「毒物及び劇物取締法」などによって禁じられていますが、大学や企業の研究室においては、科学研究の発展のために人間にとって危険なウイルスを保管、管理することが厳重な要件のもとに認められています。
この保管、管理にあたっては、同法や労働安全衛生法、同特定化学物質等障害予防規則、同有機溶剤中毒予防規則などの法令を遵守することはもとより、ウイルスが外部に漏れたり(バイオハザード)、取扱者に感染することがないように、最大限の注意義務を尽くす必要があります。
危険なウイルスが外部に漏れた場合
万が一、研究室からウイルスが外部に漏れて、人間に感染してしまうような事態が発生したとしたら、刑事上および民事上の責任が追及されることになります。
このうち、刑事上の責任は、業務としてウイルスを取り扱っていることから、業務上過失致死傷罪となり、5年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑となります。
ウイルスと感染による死亡もしくは障害との因果関係は問題になりますが、この点は「薬害エイズ業務上過失致死被告事件」の大阪高裁2002年8月21日有罪判決(主治医に対して1年6ヶ月の禁固刑の実刑)が「当裁判所の基本的立場」として、コラム(1)のように述べていることは留意すべきでしょう。
次に、民事上の責任ですが、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負うことになります。直接の過失があるものだけでなく、業務と関係のあるミスである限り、使用者も使用者責任(民法715条)を免れません。
これに対して、研究者が勝手に(無断で)ウイルスを自宅などにもちだし、そのウイルスが漏れた場合に、使用者(大学や研究所、企業など)が使用者責任を負うか否かはケースによります。すなわち、使用者が労働安全衛生法令を遵守しておらず、また、もちだしを事実上容認するなど、ルーズな管理・監督をしていたのであれば、管理、監督責任を負う可能性があります。一方、使用者としての管理、監督義務を尽くしていたにもかかわらず、当該研究者が使用者の規則に反して無断でもちだしていた場合まで、使用者に責任があるとはいえないでしょう。
いずれにせよ、ウイルスが外部に漏れるような事態が起これば、地域住民に対する信頼を決定的に失うことになりますので、厳重に注意するとともに、万が一、漏れてしまった場合には、絶対に情報や証拠を隠すことなく、ただちに関係機関および地域住民に広報して、人的被害の発生を最小限に止めるために全力を尽くすことが研究機関に求められます。
取扱者が感染した場合
この場合、不法行為責任の問題に加えて、使用者の研究者に対する労働契約上の安全配慮義務(債務不履行責任)が問題になります。主として労働安全衛生法令の定めるところですが、危険なウイルスを研究者に取り扱わせる場合には、その管理、監督には最大限の注意を払うべく、研究者に周知、徹底させる注意義務があるといえるでしょう。とくに、研究者がまだ初心者であったり、未熟な場合は、この注意義務は厳重に徹底させなければなりません。一方、ベテランの研究者で当該研究者の裁量が大きい場合には、相対的に使用者の管理、監督義務は内部的には小さくなるといえるでしょう。
この点に関連して、2004年4月12日の大阪地方裁判所損害賠償請求事件判決は、看護助手に対して、せん妄状態に陥り激しく暴れる患者に対する抑制作業の補助をさせた結果、C型肝炎ウイルスに感染していた同患者に左前腕部を噛みつかれたことにより、看護助手が唾液を介してC型肝炎に罹患し、敗血症などを発症したとして、上記補助を命じたことが安全配慮義務に違反するとされた事例で使用者(病院)の安全配慮義務違反を認めていますが、安全配慮義務の内容についてコラム(2)のように述べているのが参考になります。
いずれにせよ、こうした事故は起こってしまってからでは取り返しがつきません。これを機会にあらためて職場における危険物質の管理、監督体制のチェックをお勧めします。
コラム
ウイルスの感染事件に関する裁判所の見解
(1)薬害エイズの過失致死事件
人の生命は最も重視されるべき保護法益であって、これを凌駕する利益は存しない。したがって、濃縮血液凝固因子製剤にエイズ発症危険性があり、人の生命を侵害する危険性があるとするならば、これに対するその予見や結果回避に対する可能性及び義務については、厳しい目をもって判断するべきである。濃縮血液凝固因子製剤投与→エイズ発症→死という因果関係が、それが合理的な理由によって偶然的なものと認められる場合ではない限り、たとえ、当時、その蓋然性が高い、すなわち確実なものと認識できない場合であっても、保護法益が人の生命という高度なものである以上、予見義務や結果回避義務を否定する理由とはならないというべきである。死亡率が低いと認識していたとしても、死んだ人は運が悪かったと思えとは到底いえることではない。また、濃縮血液凝固因子製剤投与によるエイズ発症と人の生命侵害(死)との間に客観的な因果関係がある以上、濃縮血液凝固因子製剤投与によるエイズ発症は人の生命侵害という結果発生の原因力になるのであるから、この結果発生の原因力である濃縮血液凝固因子製剤投与によるエイズ発症の危険性の認識可能性がある限り、濃縮血液凝固因子製剤→エイズ発症→死という因果関係の機序等が客観的、科学的に証明されてなく、したがって、そのような因果関係の経路についての認識が困難であったしても、生じた結果についての予見可能性を肯定するのが相当である。量刑上といえども、因果関係の経路についての認識の困難性は決定的というべきではない。因果関係の経路についてまで科学的に解明され、客観的に証明されるまで予見義務や結果回避義務を負わないとかこれが軽減されるということはできない。これを肯定するならば、未曾有の悲惨な被害が出てしまうからである。この点は、これまでの公害、薬害等の事件に照らして明らかである。
(2)C型肝炎ウイルスの損害賠償事件
使用者は、雇用契約上の付随義務として、労働者が労務提供のため設置された場所、設備若しくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、その職種、労務内容、労務提供場所等の具体的状況等に応じて、労働者の生命、身体等を危険から保護するように配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。
そして、原告が勤務していた病院等の医療現場においては、医療機関としての性質上、様々な身体・精神症状を呈する患者を受け入れ、その治療のために種々の医療器具や危険な薬品を使用したり、急患等の緊急事態にも対応する必要があるなど、患者のみならず、診療・看護に従事する職員にも危険が生ずる場合があり、特に、常に病原体による感染の危険にさらされているのであるから、使用者にあっては、管理体制を整え、適切な感染予防処置を講じるなど、被用者が安全に業務に従事できるように配慮すべき義務があるというべきである。


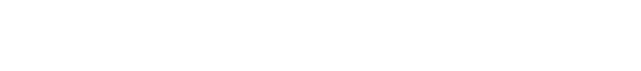
 弁護士
弁護士