学生の論文発表を禁止した
学生の論文発表を禁止した…
| 今月の相談 | 学生が、ある研究成果を修士論文公聴会で発表しようとしました。しかし、当該研究は特許出願前だったので発表を禁止したところ、学生から訴えられてしまいました。このような場合、どうすればよいでしょうか? |
|---|
特許権とは
まず特許権とは、新たに産業上有用な発明を公開した代償として国が与える権利で、特許権者(特許権をもつ者)は、特許発明を排他的・独占的に実施することができます。発明〔自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(特許法2条1項)〕が特許として成立するためには、産業上の利用性(同法29条1項)、新規性(同条1項)、進歩性(同条2項)、先願(同法29条の2、39条)、不登録事由(同法32条)の不存在などの特許要件をすべて満たさなければなりません。
新規性が重要
特許制度は発明を公開することへの代償として独占権を付与するものですから、すでに公に知られている発明に対して独占権を付与することはなく、常に新たな発明に対して付与されなければなりません。特許法2条1項各号は新規性喪失事由として、(1)公知(特許出願前に国内において公然知られた発明)、(2) 公用(特許出願前に公然実施された発明)、(3)刊行物記載(特許出願前に国内または海外において頒布された刊行物に記載された発明)をあげています。
「公然知られた発明」とは、不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明を意味し、たとえ相手が少数であっても守秘義務を負う者以外に知られた発明は、公然知られた発明となります。仮に守秘義務を課していたとしても、その者が義務に違反して他人に漏らしてしまった場合も、公知の発明となってしまいます。また「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面、その他これに類する情報伝達媒体をいうと解釈されています。
通常、修士論文公聴会における発表は、学生が所属する研究室の構成員だけでなく、学内にある他の研究室の教授など不特定多数を対象に行われたり、一般に公開される場合もあります。したがって、これは公知発明(特許法2条1項1号)に該当します。また、修士論文公聴会では、たいてい事前に研究結果をまとめたレジュメを配布するので、このレジュメが「刊行物」(同3号)に該当するとも考えられます。とすれば、学生が修士論文公聴会で研究結果を発表することによって、新規性を喪失してしまうことになります。
新規性喪失の例外
前述の特許法29条1項各号に該当する場合には、新規性がないという原則を貫くと、発明者に対して酷になりすぎるため、産業の発達を目的とする特許法の趣旨にそぐわず、かえって妥当性を欠く場合があります。そこで、新規性喪失の例外を定めた規定が同法30条です。同条1項は、「特許を受ける権利を有する者」が試験を行い、刊行物に発表し、または特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表した場合を対象としています。
「特許を受ける権利」は発明をすることによって発生し、発明の完成と同時に発明者が自動的に取得しますから、発明に実際に関与した学生は、「特許を受ける権利を有する者」に当たります。そして「研究集会」とは、研究発表を主目的あるいは重要な目的とした会合であり、修士論文公聴会はこれに該当します。
そこで、本件の大学が特許庁長官が指定する学術団体である場合には(特許庁のホームページで確認することができます)、本条の適用を受けることができます。また前述の通り、「刊行物」に発表した場合に当たることも考えられます。その場合、特許法30条を適用することによって、「新規性を喪失しない」とすることができるのであれば、発表を禁止する必要はないとも考えられます。
しかし同法30条は、あくまでも新規性喪失の例外規定であり、(1)手続き的な要件もあること、(2)例外規定の適用対象である公表のあとに第三者による同一の発明の公表があったときには、やはり新規性を喪失すること、(3)新規性喪失の例外規定がない欧州各国では特許権の取得が困難となるリスクがあることから、やはり公表前に特許を出願すべきでしょう。
今回の相談の場合では?
今回の場合は、特許出願前であることを理由に公表を禁止することが問題となります。まず、学生に論文の発表を禁じたのが大学なのか、学生の指導教官なのか明らかではありませんが、大学の場合、そもそも学生が本件の発明を公表することに大学は利害関係をもつのでしょうか。発明は事実行為ですから、法人自体による発明はありえません。すなわち大学は、現行特許法において、発明者にはなれないのです。しかし、「特許を受ける権利」は移転できるため、大学は発明者から「特許を受ける権利」を承継することができます(特許法33条)。また、指導教官や共同研究者など複数の者が実際に発明に関与したとすれば、「特許を受ける権利」は共有となり、各共有者はほかの共有者と共同でなければ特許を出願することができません(同法38条)。ただし、大学が共同発明者である指導教官あるいは学生自身から「特許を受ける権利」を承継していた、または承継する予定がある場合(あるいは端的に教官などによる職務発明として機関帰属する場合)でも、ただちに学生に対して論文の公表を禁止することはできません。
したがって、大学がプロジェクトとして位置づけている研究など、とくに重要な研究については、あらかじめその研究に関与させる学生とのあいだで共同研究契約あるいは研究委託契約を結び、そのなかで守秘義務を課す、あるいは秘密保持に関する誓約書を提出してもらうべきでしよう。大学と学生がこのような契約を締結すること自体は、民法上の契約自由の原則により有効です。そうすれば、私的自治の原則に基づいて、学生は守秘義務ないし秘密保持義務に拘束されることとなるので、学生に特許出願前の論文発表を禁止することに対して訴えられるといった争いを防ぐことができます。また、研究室の教授が学生と秘密保持義務に関する契約を結び、これに基づいて発表を禁止した場合も同様に考えることができます。
コラム
刊行物の該当性
刊行物(特許法29条1項3号)の該当性に関する判例としてクロス論文事件(東京高裁平成5年7月29日判決)がある。外国のA大学から博士号を取得するために作成した論文について、少部数制作されたハードカバー本のうち1冊がA大学の図書館に受け入れられた。その本は希望者が自由に閲覧できる状態に置かれ、また申請により希望者には論文の写しが交付される態勢にあった。この場合について東京高裁の判決では、A大学図書館に申請して取得された同論文の複写物は「外国において頒布された刊行物」ということを妨げないとした。
複写物の刊行物性に関する判例としては、「刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものを指すところ、ここに公衆に対し頒布により公開することを目的として複製されたものであるということができるものは、必ずしも公衆の閲覧を期待してあらかじめ公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているものとしなければならないものではなく、右原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っているならば、公衆からの要求を待ってその都度原本から複写して交付されるものでも差し支えない」と判断した最高裁昭和55年7月4日判決がある。つまり、原本が公開され、かつ何人も自由にコピーできるものであるなら、そのコピーは刊行物に該当するという意味である。


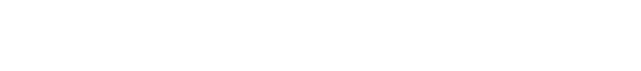
 弁護士
弁護士