事件報告 死亡危急時遺言(しぼうききゅうじゆいごん)という制度
身寄りはないが知人に遺産を残したい
ある病院の緩和ケア病棟に入院中だったAさん(当時78歳)。がんを患い、医師からは余命はそう長くないと告げられていました。
そして、Aさんには身寄りがありませんでした。父と母はすでに亡くなり、兄弟はおらず、結婚もしておらず、子どももいません。ですが、Aさんは、数十年来、趣味をともにしてきたBさんと深い親交を持っていました。Bさんも、Aさんが病気で入院したときなどには身の回りの世話をしてくれており、Aさんとしても、亡くなった後の葬儀や永代供養の手配など、全てBさんにお願いしていました。そのため、住んでいた住居や預貯金などの遺産については、Bさんに全てもらってほしいという希望をお持ちでした。
Aさんを担当するソーシャルワーカーが、Aさんよりそのような希望をお聞きしたことから、当事務所に相談依頼の連絡が入り、Aさんが入院されている病院まで出張して相談をお聞きすることになりました。
Aさん自身から、上述のような状況や希望を一通りお聞きし、Aさんのお身体の状態(Aさん自身は手に力が入らず筆記ができない状態でした)からしても遺言の作成が急務であると判断し、その足で公証人役場へ向かい、公証人と打合せをして、1週間後に公証人が出張して公正証書遺言を作成する段取りをつけました。
死亡危急時遺言の作成
ところが、2日後の朝、病院からAさんの容態が相当悪い状態になっているとの連絡が入りました。翌週の公正証書遺言の作成を待ってはいられません。他方で、上述のとおり、Aさんは自分で遺言を書ける状態ではありませんでした。そこで、担当のソーシャルワーカーを通じて、死亡危急時遺言を作成することとしました。
遺言の文案と、死亡危急時遺言の要件(①証人が3名必要であること、②遺言者(Aさん)が証人の1人に遺言の内容を口頭で述べて、その証人が筆記すること、③筆記した証人が、遺言者(Aさん)と残りの2人の証人に遺言の内容を読み聞かせて、筆記の内容が正確なものであることを承認すること、④証人による署名押印)については、担当のソーシャルワーカーとの間で、ファックスと電話でやりとりをして正確を期し、病院職員3名が証人となって、無事、午前中のうちにAさんの死亡危急時遺言が作成されました。
そして、Aさんは遺言を作成された日の夜、息を引き取られました。
身寄りのない方の相続はどうなるの?
このとき、Aさんの遺言が作成されていなかったとしたら、一体どうなっていたのでしょうか。
上述のとおり、Aさんには身寄りがありません。仮に、遠縁の親戚がいたとしても、その方々はAさんの相続人ではありません。もちろん、親族関係のないBさんは相続人ではありません。
このように相続人がいない場合、その遺産は原則として国庫に入ることとされています。家庭裁判所により相続財産管理人が選任され(多くは弁護士が選任されます)、不動産や有価証券などを処分して換金した後、国庫に納入されることとなります。Bさんとしては、その手続の中で「特別縁故者」として財産の分与を受けることができるとされていますが、分与されるか否か、どれだけの財産が分与されるかについては、あくまで家庭裁判所の裁量に任されています。
ですので、Aさんの場合、遺言が作成されなければ、Aさんの生前の希望はほとんど叶わなかった可能性が高いのです。
死亡危急時遺言のその後
そのようにして作成されたAさんの死亡危急時遺言ですが、作成されればそれで終わりではありません。そもそも死亡危急時遺言は、遺言者が普通の方式の遺言(自筆証書遺言や公正証書遺言など)をできるようになったときから6か月間生存したときには、効力を失ってしまいます。
そして、死亡危急時遺言の場合、遺言の日から20日以内に、家庭裁判所に対して確認請求をしなければなりません。この死亡危急時遺言の確認手続では、家庭裁判所が、遺言が真意によるものかどうかの判断を下します。さらに、家庭裁判所の確認決定を得た上で、自筆証書遺言の場合と同様、家庭裁判所の検認手続を経て、ようやく遺言に基づく登記や名義変更が可能になるのです。
今回のケースでも、そのような家庭裁判所の手続を経て、無事、Aさんが生前望んでいたとおり、Bさんに遺産を受け取っていただくことができました。いつ何が起こるか分からないのが人生です。早め早めの対応が大切ですので、元気なうちに弁護士へ相談されることをおすすめします。


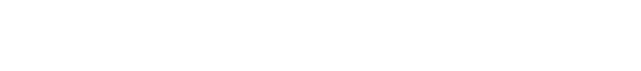
 弁護士
弁護士