ある野球少年の熱中症死亡事故事件
野球少年の熱中症死亡事故
2005年10月初旬、「特訓の中2熱中死」「投げ込み1時間、20mダッシュ100本、30mダッシュ100本、坂道ダッシュ200本」「野球大会敗戦のペナルティ」という活字が新聞記事に大きく踊っていました。京田辺市にある少年野球チームに所属する中学2年の男子生徒O君が試合後の敗戦の罰として猛特訓の最中に熱中症で倒れ、救急車で病院に搬送されましたが、翌日死亡するという内容でした。未だにこんな練習が行われているのかと驚きましたが、10月に入ったばかりでも熱中症になるのかという疑問も感じました。
ところが、10月下旬ある人の紹介でO君のご両親から相談を受けることになりました。ご両親は、O君の野球の才能に期待し、将来はプロ野球選手をめざすことも夢見ていたのですが、どうしてこんなことになってしまったのか、チームの責任者であるK総監督からは何ら説明もなく、納得できないので、事実を解明して、責任の所在を明らかにしてほしいという依頼がありました。
有名な少年野球チームに所属
この少年野球チームは、京都田辺硬式野球部という、主として中学生を対象とした硬式野球を指導するクラブチームで、日本最大の少年硬式野球組織である日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)に所属し、全国大会、関西大会等の主要な大会で毎年優勝ないしそれに準ずる成績をあげる全国でも強豪チームとして知られていました。チーム出身のプロ野球選手も多く、現役では内海選手(巨人)や今江選手(ロッテ)などがいます。
O君は、小学4年から野球を始め、京都田辺野球部に入部し、全国大会に出場するなど活躍しました。中学生の部に入部した最初の1年間はレギュラーにはなれず、練習に明け暮れました。練習は、平日は午後5時から午後9時頃までは、土・日曜には午前9時から午後6時頃まで行われ、休みは週1日しかなく、ほとんど毎日のように行われていました。中学2年の9月、2年生を中心とした新チームが発足し、O君は13歳ながら身長185cm、体重90kgと堂々たる体格で、エースで4番の文字どおり新チームの大黒柱となっていました。
死亡事故当日の経緯
2005年10月1日-ボーイズリーグ主催の関西秋季大会京都府予選が行われ、京都田辺はこれに出場しました。O君は、午前5時30分に起床して自宅を出発し、午前6時30分から打撃練習と軽いアップ練習を行い、球場に向けて出発しました。第1試合では、O君は4番ファーストで先発出場し、京都田辺が勝利しました。昼食後の第2試合では、O君は4番ファーストで先発出場し、4回からリリーフ登板しましたが、四球や失策などもあり、結局京都田辺は敗戦しました。敗戦後、K総監督は、「ペナルティ」としての練習を行うと宣言し、選手たちに指示しました。チームは練習グランドに到着し、敗戦試合のミーティングを行った後、午後5時30分頃から、「ペナルティ練習」が開始されました。
まずO君を含む投手・捕手は、連続10球ストライクが入るまで投球練習を指示されましたが、全力投球で10球続けてストライクを投げるのは相当困難で、午後6時20分頃日没となり、ボールが見にくくなったため、投球練習は終了しました。投球練習終了後、K総監督は、5分程度休憩させただけで、20mダッシュ100本を指示しました。この練習は全速力で20mを走り、またこれを繰り返すというもので約30分繰り返されました。続いて、30mダッシュ100 本の指示があり、O君は、最初は遅れずにいましたが、ちょうど半分くらい経過した頃から他の部員たちから遅れ始めていました。さらに、木津川の土手の堤防の斜面(長さ約8m)を利用して駆け上る坂道ダッシュ200本の特訓が命じられました。O君は、1回目の100本から足取りが重く、他の部員から遅れており、最後は足がふらついていましたが、何とか100本を完遂すると、斜面の上部で大の字に倒れて動けない状態になりました。5分ほどの休憩があり、午後8時30分頃2回目の100本が始まりましたが、O君はふらふらしながら数本ダッシュした後、斜面の下部で再び倒れましたが、K総監督は倒れたO君の姿を見て、「放っておけ。いいから寝かせておけ。」と言うだけで、O君のところに近づこうともしませんでした。O君はしばらく寝かされたままの状態でしたが、全く動かない異変に気づいた保護者らが様子を見たところ、意識がないことが分かり、午後9時13分にようやく救急車の要請がなされ、午後9時20分救急隊が現場に到着し、O君を収容し、午後9時26分現地を出発し、午後9時45分病院に到着しました。病院到着時のO君の状態は昏睡状態であり、体温 40.4℃、熱中症、急性循環呼吸不全と診断され、治療が開始されましたが、回復せず、翌2日午後9時58分、DIC、多臓器不全のため死亡するに至りました。

坂道ダッシュが行われた堤防の斜面
ご両親の思い
O君の死亡原因は熱中症であることは医師の診断書により明らかでしたが、どうしてこんなことになったのか。その責任はどこにあるのか。ご両親としては、これに明らかにしてほしいという思いから、2006年3月K総監督を相手として民事訴訟に踏み切りました。
この訴訟において、K総監督が行った答弁は、練習内容は決めていたものの、その実施は各選手の自主性に任せており、適度な休憩と水分補給も行っており、O君の事故は、O君の睡眠不足からきた体調不良が原因となって発生した不慮の事故であり、責任はないと正面から反論してきました。挙げ句に、練習中のグランド周辺にご両親がいたことから、倒れたO君の安全を確認できたであろうから過失相殺がなされるべきというとんでもない主張まで繰り出してきました。
確かに、スポーツ練習中の熱中症による死亡事故の事案では、保護者の面前で事故が起こるようケースはほとんどありません。しかし、京都田辺は、K総監督の絶対的な指揮監督下にあったのです。K総監督の野球「塾」であり、野球に関することであれば、保護者はK総監督に逆らうことは一切できなかったのです。保護者は、K総監督に刃向かうと、自分の子どもが試合から外されてしまうのではないか、高校入学に影響が出るのではないかという不安があったのです。だからK総監督に逆らったり、意見をしたりする保護者は誰一人としていなかったのです。
少年野球チームの解散
日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)も、その加盟する野球部に起こった事件であることから、調査を行い、その結果として、K総監督は除名、京都田辺野球部は解散という処分を受けました。処分理由として、(1)関西秋季大会予選で敗退後、ペナルティと称する中学生には耐えられないほどの過酷な特訓を長時間強行し、同チームのO君(2年生)がその特訓中の最終段階で倒れ、熱中症による多臓器不全で死亡するという痛ましい事件が発生したこと、(2)その特訓の指揮を執ったのが同チームのK総監督で、選手の健康管理への配慮を全く欠いた無謀ともいえるそのやり方は、ボーイズリーグの精神から大きく逸脱したものであったこと、(3)しかも、その特訓が日本少年野球連盟の規定で認められていない、夜間に行われたものであったこと、(4)京都田辺野球部の解散は、O君を死に至らしめたようなペナルティ特訓で作り上げられた、また「勝つことだけがすべて」(京都府支部関係者)という体質のチームを存続させては、今度もこれに類似する事件を起こす危険が十分にあるため、とされています。
民事裁判の経過
訴訟においては、K総監督の過失(選手に対する安全配慮義務違反)を立証する必要があります。K総監督は、10月に入っていたことから熱中症にかかるなどとは思ってもみなかったようでした。実際にも、O君が倒れて動かなくなってからしばらく経ってから、O君のところに行き、身体が冷たくなっているとして、保温クリームを塗布したくらいでした。
しかし、10月とは言っても当日の最高気温は28.2℃で平年に比べ約4℃も高く、グランドの気温は輻射熱の影響によりさらに4~5℃は高いと考えられます。また、事故当日、O君たちは、午前6時30分から野球の活動を開始し、2試合をこなした上で、練習グランドに戻ってきた時点ですでに10時間もの長時間にわたり、野球の活動が続き、相当体力を消耗していることは十分予測できるところでした。このような状況の下では、心身の発達途上にある当時13歳の中学2年の肉体的疲労は相当な程度に達していたのですから、さらに体内の筋肉から大量の熱が発生する練習を行えば、真夏の炎天下でなくとも、熱中症の危険があることは、過去の熱中症死亡事故事例からも明らかでした。
そもそも熱中症とは、身体の中と外の「熱さ」によって引き起こされる様々な体調不良の総称であり、熱さのために身体の水分や熱のバランスが崩れ、正常な体温維持機能が阻害されることによって生じます。気温が高いと熱中症の危険が高まりますが、特にスポーツ活動中においては、体内の筋肉から大量の熱が発生することから、熱中症の危険が高く、短時間の運動やそれほど気温が高くない条件下においても、熱中症が発生しています。熱中症の死亡事故が起こっている種目の中でも野球が圧倒的に多く、ダッシュ、ランニングの繰り返しによるものが多いことが報告されています。湿度が高いとき、風のないとき、あるいは厚手の衣類を着用しているときは、汗をかいても蒸発しにくく、体内の熱を放射することができず、体温を下げる効果が落ち、熱中症にかかりやすくなります。さらに、性格的に、真面目、我慢強い人は、めまいや頭痛などの熱中症の症状が出始めているのに、それを我慢して練習を続ける結果、重篤な状態になってしまいます。熱中症は、原因、症状、程度により、(1)熱痙攣、(2)熱疲労、(3)熱射病の3つに分類されますが、熱射病は最も重篤な病態で、体温調節機能が破綻した状態で、昏睡などの意識障害が起こり、手当が遅れればショック状態となり、体内の血液が凝固し、多臓器不全となり、死亡する危険性が高く、迅速な医療措置が必要で、発症後20分以内に体温を下げることができるかどうかが救命の鍵とされています。
この点につき、熱中症に関する第一人者である国立スポーツ科学センターの川原貴先生(医師)に意見書をお願いしました。意見書の要旨は、10月としてはかなり暑い日に早朝から長時間のスポーツ活動をして疲労した状態で、さらに過酷なペナルティ練習を十分な水分補給や休憩もなく長時間行ったことにより熱中症を発症して死亡したものであり、O君が倒れて動けなくなった時点で異常を疑い、すぐに駆けつけて身体の様子を見ていたら、身体が異常に熱くなっていたことに気づき、熱中症に罹患したことが分かったと思われ、その時点で直ちに救急車を要請するなど適切な対応をしていれば、救命できた可能性があるということでした。
和解の成立
こうしたK総監督の過失の立証活動の結果、2007年9月14日付けで裁判所も、K総監督は、O君の身体の状況に気を配り、遅くとも2回目の坂道ダッシュ開始直後にO君が倒れた時点では、O君の容体を観察してO君が熱中症に罹患していることを把握し、身体を冷やすとともに、直ちに救急車を手配するなどして適切な措置をとるべき注意義務があったのに、これを怠った過失があると見解を明らかにし、和解勧告を行いました。
O君のご両親は、基本的には原告の主張する事実認定に立って、K総監督の過失を認め、プロ野球選手になるという自らの夢を実現するため、厳しい練習に一生懸命ついていこうとした結果、皮肉にも若くして逝くことになってしまったO君の無念さや、生活の中心にいたO君を失ったことによる親族らの悲しみを考慮した裁判所の和解案を受け入れることにし、同年10月19日和解が成立することになりました。
和解内容(骨子)としては、(1)被告は、京都田辺硬式野球部の総監督として、亡O君を長時間にわたって過酷な練習をさせ、しかもO君が倒れたときに適切な処置をとらなかった結果、熱中症に罹患して死亡するという結果を生じさせたことにつき、その責任を認め、衷心から謝罪する(和解案の過失に関する裁判所の見解を受け入れる)、(2)被告は、将来において少年野球の指導にあたる場合には、熱中症に関する知識を十分に習熟して、熱中症の罹患を防止するための最大限の努力をすることを誓約する、(3)被告は、原告両名に対し、和解金として金○○○○万円を2007年11月20日限り支払うというものでした。和解条項以外にも、被告は、亡O君の霊前にお参りし、亡O君および原告らに対し謝罪するとともに、亡O君の冥福を祈ることを行うことが決められました。
熱中症に対する知識の普及を
和解条項として謝罪文言を入れたこと、および亡O君の霊前で実際にK総監督が謝罪してもらうことを約束させたことは、判決では勝ち取れないものであり、最愛の息子を失った原告ら両親にとっては、きわめて大きな意味があります。また、スポーツ指導者においても、なお熱中症に関する知識が不十分であり、科学的なトレーニングが実施されていないことを告発し、啓蒙することが、本件訴訟のもうひとつの大きな目的でしたが、これも一応達成することができました。熱中症は、炎天下の環境においてだけでなく、10月といった時期であっても、気温・湿度、運動強度、疲労の程度などの諸要素が複雑に絡み合って起こる可能性があります。だからこそ、スポーツ指導者は、そのような基礎知識をもとに、様々な状況を的確に把握し、あわせて選手個人の事情も総合考慮して、熱中症防止に万全の対策を講じなければなりません。本件では、K総監督が遅くともO君が倒れて動かなくなったときに異常を感知し、直ちにO君の体調を具体的に把握する努力をしていれば死亡という最悪の結果を回避できた可能性が大きい。和解金額については、裁判所が和解案において認定した損害総額は同種事案における判決を上回ったものであり(特に慰謝料の算定においては厚くなっている)、和解ということから若干の調整があったものの、実質的には勝訴と評価することができます。
亡くなったO君が生き返ってくるわけではなく、ご両親の悲しみは決して癒えることはないでしょう。しかし、この裁判を通じて、最愛のわが子がどうして亡くならなければならなかったのかが明らかになり、また熱中症に関する知識がスポーツ指導者を始め、たくさんの人たちに広まることにより、熱中症事故の防止につながることが亡くなったわが子の最良の供養になると信じておられます。合掌。





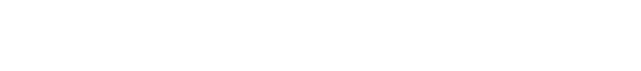
 弁護士
弁護士


