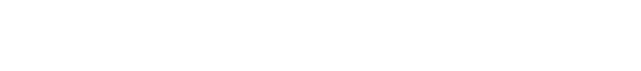公益法人改革に伴う新たな課税問題への対応
 税理士 山本龍男
税理士 山本龍男公益法人を「2階建て」にして
第164回通常国会(平成18年)において、「公益法人制度改革関連3法」が成立し、平成18年6月2日に公布されました。
従来、わが国の社団法人・財団法人(民法第34条法人)は主務官庁によって設立の許可、公益性の判断が一律的に行われてきました。
新法の施行後は、登記(準則主義)で設立する「一般社団・財団法人」と、有識者意見を基に内閣総理大臣又は都道府県知事が「公益性の認定」を行う「公益社団・財団法人」の2階建ての制度に改められます。
公布された「公益法人制度改革関連3法」とは、
- (1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
- (2) 公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律
- (3) (1)(2)の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)
の3本です。
この法改正に伴って、約26,000件あると言われている現存の社団法人、財団法人は施行日から5年以内に、移行登記により一般社団法人、財団法人に、又は、認定申請により、公益社団、財団法人に移行できる措置がとられます。
移行登記や認定申請を行わない場合は名称の中に「社団・財団」の文字を使用することができませんし、原則5年間の移行期間の満了により、解散したものとみなされます。
関連3法の施行日は、平成20年12月1日までに政令できめられ、「公益認定等委員会」の設置の施行日も平成19年12月1日までにきめられます。
「公益認定」は内閣府内に有識者7名からなる合議制の「公益認定委員会」が設置され、認定作業を行います。(都道府県にも設置)
収益事業課税方式から全所得課税方式に
現行法人税法第4条第1項、公益法人等や人格のない社団等は、原則非課税とされ、限定列挙された33業種の「収益事業」を営む場合に限り課税されることになっています。
しかし、政府は公益法人改革を推し進めるにあたって、法人には「すべて納税義務がある」との前提で見なすことを平成15年6月27日の閣議で決定しました。
公益法人・非営利法人が課税を受けないのは、そもそも非収益事業に納税義務が生じないからではなく、税制上の優遇措置によって免除されるからだという組み立てにしました。
公益法人・非課税法人は収益事業を営んでいなくても、又、構成員に対して利益分配を行っていなくても、まずすべての所得に課税されることになります。
一定の条件をクリアーして認定公益法人になれば、税制上の優遇措置として具体的な課税ベースの範囲内で対応されることになるようです。
その一定の条件とは
- (1) 公益目的事業が主目的
- (2) 公的目的事業にかかる収入が、その実施に要する適正費用を超えることはないか
- (3) 公的目的事業比率が100分の50以上の見込みか
- (4) 同一親族等が理事又は監事の3分の1以下か
- (5) 理事等の報酬等の支給基準を公表
- (6) 遊休資産額が一定額を超えないこと
- (7) 寄附金等の一定の財産を公益目的事業に使用、処分
- (8) 財産目録等を備え置き、閲覧、行政庁へ提出
- (9) 認定取消等の場合、公益目的で取得した財産の残額相当額の財産を類似の事業を目的とする他の公益法人に贈与することを定款に定める
等が考えられているようです。
現存の26,000余の社団法人・財団法人は平成20年12月1日を期限にして、前記の条件をそれぞれの法人の実状に合わせて、一般法人、一般公益法人、認定公益法人の選択をしなければならないし、これまでの収益事業課税方式から全所得課税方式へと変わります。
又、取消になった時や、ランク落ちした時に、これまでに蓄積された財産や、構成員への分配があればそれへの一定の課税も検討されることになると推測されます。
平成19年度税制改正では、4月の統一地方選挙、7月の参院選挙があるためか、公益法人・非営利法人に関する改正は提案されていません。
しかし、政府の増税政策が、政府税制調査会の答申に沿って実行に移されており、今後の政府税調、同関係委員会、経済財政諮問会議等の討議の行方を把握しつつ、移行期間内に結論を出さなければなりません。認定公益法人に移行するのであれば、条件の充足に耐えうるのか、一般公益法人や解散等を選択するのであれば、課税対策を如何に立てるのかが重要になるため、その選択に際しては慎重さが求められることは間違いありません。
最後にこの問題は、
- (1) 特別法上の公益法人(学校法人、社会福祉法人宗教法人、NPO法人等)に対する課税
- (2) 地縁団体(町内会、自治会等)、マンション等の管理組合、人格のない社団等(労組、生産組合、各種任意団体等)に対する課税
- (3) 収益事業(限定33業種)の見直し
- (4) 寄付金や会費収入に対する課税と範囲の見直し
等々の諸問題に波及していくことは必至であり、今後の課税強化の方向に、どのように対処していくのかが極めて重要となっています。