原告らが理解できる裁判を求めて(残留孤児国家賠償請求京都訴訟)
原告らの本人尋問が始まりました
2005年2月、残留孤児国賠京都訴訟の原告本人尋問が始まりました。6月までの5ヶ月間の間に、月2回、1回当たり終日かけて、原告本人12名、証人2名の尋問が行われ、秋にも結審の見込みです。2003年9月24日の提訴から1年半、裁判は、いよいよ正念場にさしかかってきました。
2月17日の本人尋問に立ったのは、奥山イク子さん(原告団長)でした。
奥山さんは、9歳の時に満州に渡り、12歳の時に終戦を迎えました。その後は、中国人のもとで育ち、日本語をすっかり忘れてしまいましたが、57歳の時に日本に永住帰国し、並々ならぬ努力で日本語をマスターし、日本語で会話をすることができます。
しかし、奥山さんのように日本語を理解できる孤児は滅多にいません。終戦時、多くの原告達は幼く、産まれてすぐに中国人に預けられた孤児達は、日本語を聞いたこともありません。そして、日本に帰国するのは、原告達が50歳代、60歳代になってからなのです。私たちが、50歳、60歳になってから、中国語を一から覚えなさいと言われたとして、果たして中国語を普通に話すことができるようになるでしょうか。
孤児達が、今でも日本語を満足に話すこともできず、困難な生活を強いられていること、その原因の一つは、孤児達の帰国が遅れたことにあり、それは国の責任によるものであるこ と、これが、この訴訟の大きな争点であり、全国13の裁判所で、2000人近い孤児達が国を訴えて裁判を闘っている大きな理由の一つです。

中国残留孤児国家賠償訴訟の勝利をめざす
3・21 全国総決起集会 デモ行進
日本語がわからない原告と中国語がわからない裁判所
ところで、裁判は、当然のことながら日本語で行われます。私たち弁護団も、裁判官も、国の代理人も、誰一人中国語が分りません。多くの原告達は、中国語しか理解できません。一方特に、一般の人たちにとっても難しい裁判でのやりとりを日本語で行うことなどとてもできません。そこで、原告が中国語で証言する場合は、通訳が日本語の質問を中国語に、原告の答えを日本語に訳すことになっています。
しかし、私たち弁護団は、奥山さんの他にも日本語を話すことができる原告の方達には、なるべく日本語で証言してもらうことにしました。通訳が訳した言葉ではなく、原告の生の声を裁判官に聞いてもらいたかったのです。
そこには、問題が一つだけありました。というのは、証言が日本語で行われた場合、原告達の多くは、裁判で何が行われているのか、全く理解できなくなってしまう、ということです。朝10時から夕方5時まで、何をしているのかさっぱりわからない法廷の傍聴席にじっと座っていることくらい耐え難いことはありません。特に、原告達は、傍聴人ではなく、裁判の当事者であり、主人公です。自分の裁判の内容を知る権利があります。
弁護団は、日本語でのやりとりを中国語に訳すよう、激しく裁判所に迫りました。中国では置き去りにされたあげく日本人であるとして迫害され、日本では中国人と呼ばれて差別され、社会から阻外されていることが被害の根幹であるのに、自分の裁判からも阻外されることは許されない、と。国側は激しく抵抗し、今でも抵抗を続けていますが、全国で初めて、日本語でのやりとりを中国語に通訳することが実現しました。
初めて裁判を受ける権利が実現できた
奥山さんは、法廷で、5時間にわたり、時には涙を抑えながら、時には力強く証言をしました。
傍聴席の原告達は、いずれも真剣に通訳の言葉に耳を傾け、時にはすすり泣く声が聞こえ、奥山さんの最後の訴えには思わず拍手がわき起こりました。
原告や支援者の集会では、初めて自分達の裁判を受ける権利が実現された、と喜びの声があがりました。
ところが、自分の裁判の内容を理解する、この当たり前のことが、なかなか認められないのです。
先頃、大阪と神戸の裁判でも、日本語の中国語への通訳が認められました。神戸では、国際会議の同時通訳などで用いられるヘッドホンが使用され、同時通訳がされたとのことです。しかし、京都、大阪、神戸以外の裁判所では、今でも通訳が認められていません。原告達は、弁護士や裁判官、証人達が何を話しているのか分らないまま、大きな阻害感を味わいながら、法廷に座っているのです。
最後に
残留孤児達が、中国でどのような体験をしてきたのかは、意外に知られていません。この裁判は、残留孤児のことはもちろんのこと、戦争が引き起こした被害がどういうものだったのか、何より戦争によって一番の被害を受けるのは子供達であることなどについて、戦争の被害者の生の声を聞くことができる数少ない機会です。ぜひ、原告らの尋問を傍聴して下さい。

2005年2月18日付 京都新聞


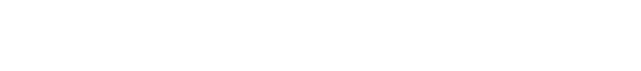
 弁護士
弁護士