個人再生手続 いよいよ4月1日より施行
いよいよ4月1日より施行
2000年秋の臨時国会において、民事再生法の特則として、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続が立法化され、あわせて成立した住宅ローン債権の特則とともに、本年4月1日より施行されています。
本手続の制定は、自己破産申立件数が13万件に達し(2000年)、潜在的・予備的破産者やその一歩手前という層を含めると150万人以上とも言われる膨大な層になる中で、今まで、破産か任意整理もしくは調停しか事実上選択肢が無かった多重債務者の生活再建にとって、画期的な意味をもつものです。
アメリカ連邦破産法では従来から清算型手続とともに、再建型手続として13章手続(債務調整手続)があり、かねてより日弁連やクレジット・サラ金対策協議会などは個人の生活再建を容易にする制度の制定を求めてきたところです。
個人が利用し易い民事再生の特則手続の誕生は、多重債務者の生活再建について、新しいメニューを用意するもので、今後大いに活用していくことが期待されています。2000年の京都地裁の自己破産申立件数は3000件を超えましたが、本手続は、初年度で京都だけで1000件、即ち自己破産件数の3分の1程度の利用が想定されています。
小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続の概要
破産手続をとるか、本手続をとるかは、債務者の選択に委ねられています。債権者から本手続を申立てることはできません。
利用できるのは、消費者、勤労者、自営業者など個人に限られます。
本手続においては、財産(不動産、車、生命保険など)については、そのまま維持することができます。最低返済額は100万円もしくは債権額の5分の1のいずれか多い額(但し、5分の1が300万円を超える場合には300万円)とされています。
但し、清算価値(=破産した場合)以上の返済はしなければなりません。
本手続をとるためには、負債の全体額を明らかにする必要があります。利用できる負債の上限額は住宅ローン債権や別除権(=抵当権など)の行使によって債権者が返済を受けられる額などを除き3000万円とされています。
申立て時に利息制限法の引き直し計算ができない場合には、とりあえず、推測の債権額を書いておき、後日資料を債権者に出させたうえで、利息制限法にもとづいて再計算するために、申立て時に異議を留保しておく必要があります。弁護士を代理人につけない場合には、裁判所が個人再生委員(原則として弁護士)を選任して、債務者の手続上の援助をすることになります。
給与所得者等再生手続は、収入がほぼ定額(サラリーマン、年金生活者など)な方について利用できる特則で、債権者の同意は不要です。その代わりに原則3年間(5年まで延長可)で2年分の可処分所得(収入から生活保護基準を参考にして政令で定められる生活費を控除した額)を計画的に返済する必要があります。
他方、小規模個人再生手続は、定期的な収入の見込みがあれば、自営業者等にも利用できますが、再生計画について債権者数の半数もしくは議決権総額の2分の1を超える不同意があれば、認められません。
再生計画を遂行すれば、当然に残債務は免責されます。遂行が困難になった場合は、2年を限度として期限を延長する再生計画の変更も可能です。4分の3以上の返済をした時点で不履行になった場合には、事情により免責を受けられる場合(ハードシップ免責)もあります。
住宅ローンについては「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用できます。即ち、過去の不履行部分について、3年ないし5年以内に弁済する計画を策定できれば、「期限の利益」を回復することができます。それが無理でも、10年を超えず、債務者の年齢が70歳を超えない範囲で分割返済期限を延長(リスケジューリング)することができます。
どのような場合に活用できるのか
これまでは、多重債務の法的救
済手段としては、(1)自己破産申立、(2)任意整理、(3)調停(特定調停もしくは債務返済協定調停)しか方法がありませんでした。
自己破産申立が一般的な対応でしたが、(1)自己破産を避けたいと希望するとき、(2)今の購入した住宅に住み続けたいとき、(4)今の商売をそのまま維持したいとき、(3)免責不許可の可能性があるとき(ギャンブル、浪費、詐欺的な借入れ、不平等な返済など)、(4)破産に伴う資格喪失を避けたいときなどには、破産申立は躊躇せざるを得ません。他方、任意整理や調停をするためには、分割返済の場合には、利息制限法に引き直して、3年程度(最長でも5年程度)で全額返済することができるか否かが、一つのメルクマール(指標)となっていましたが、多くの場合困難をともないます。
このような場合には、これからは、個人再生手続による救済が基本となるでしょう。
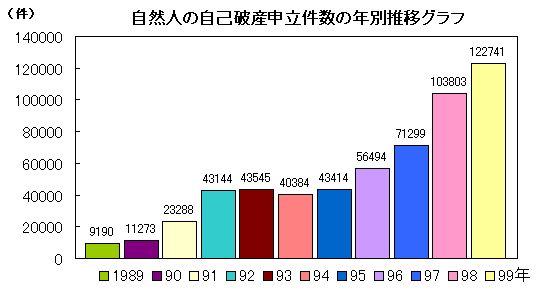


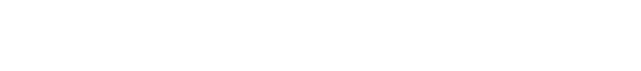
 弁護士
弁護士