新型コロナウイルス感染症に関連して解雇や雇止めをされた方は、把握されているだけで、見込みを含めれば5万人を超えています(2020年9月1日時点。厚労省発表)。ほかにもいろいろなトラブルがあると思われます。
そこで、当事務所に寄せられた相談を含めていくつかピックアップして解説しました。お困りのことがあればすぐにご相談ください。
【Q1】感染拡大防止のためということで会社がしばらく休むことになりました。休みになっている間の給料はどうなりますか?
まず、自分には働く意思のあることを会社に明示した上で、少なくとも平均賃金の60%の休業手当を請求しましょう(労働基準法26条)。この手当は使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合に使用者が支払義務を負うもので、使用者の責めに帰すべき事由という要件は、労働者の生活保障の観点から緩やかに解釈されています。新型コロナウイルス感染症による会社の休業の場合でも、基本的には使用者の責めに帰すべき事由があるものとして労基法26条の要件を満たすと考えられます。
さらに、民法536条2項は、「使用者の責めに帰すべき事由」がある場合には給料を支払わなければならないとしています。「コロナでお客さんが減っているから」「政府が自粛を呼びかけているから」などの場合、使用者が労働者に労務を提供させること自体はできると思われますので、多くの場合には民法536条2項により給料全額の支払義務が発生すると考えられます。この場合、労働者は給料の全額を支払うよう請求することができます。
労基法26条の場面なのか民法536条2項の場面なのかは、緊急事態宣言の発令中か否か、政府自治体からの自粛要請の有無やその内容などによってかわってくる場合もありますので、まずは現状をよく確認しましょう。
【Q2】仕事が減ったということで、シフトを減らされてしまいました。どうすればいいでしょうか?
出勤した日数に応じて給料が決まるという場合、ポイントはどの程度(例えば月に何日くらい)仕事をするかということが労働契約上定まっているかどうかです。労働契約書で「月に○日勤務」ということが明示されていれば、その内容で労働契約が成立していることになりますので、それを下回る日数しかシフトが入らなかった場合、Q1のように民法536条2項に基づいて給料の全額を請求することができると考えられます。
労働契約書に明示されていなかった場合でも、そのような約束があったり、あるいは実績として少なくとも月にこのくらいの日数は仕事をしていたという事実があれば、その内容で労働契約が成立していると考えられます。
労働契約書やそれまでの勤務実績を確認しましょう。
【Q3】会社が新型コロナウイルス感染症の影響を理由に解雇や雇止めをしてきた場合、どうすればいいでしょうか?
労働契約に期間の定めがない場合、使用者が労働者を解雇するためのハードルはとても高く、客観的合理的理由と社会的相当性が必要です(労働契約法16条)。新型コロナウイルス感染症によって業績が悪化したことを理由とする解雇の場合、いわゆる「整理解雇」という類型に該当し、労契法16条を満たすかどうかの審査がより厳しくなります。解雇を回避するための努力を尽くしたかどうか、労働者や労働組合にきちんと説明をしたかどうかが問われるのです。
労働契約に期間の定めがある場合、期間途中の解雇については上記と同様です(「やむを得ない事情」が必要なので、よりハードルが高い)。期間満了により更新をしないという雇止めの場合も、解雇の場合と同様に高いハードルが課せられています(労契法19条)。この場合、契約の更新回数や通算労働期間、契約書の更新に関する記載(「更新あり」となっているか、あるいは不更新条項があるかなど)等が問題になります。
いずれの場合でも、会社はまず自主的に辞めさせようとしてくることが多いと思われます。退職届を出すなどして自ら辞めてしまうと、後からそれを争うことは非常に難しくなりますので、退職勧奨を受けた場合、少なくともその場で応ずるということだけはしないようにしてください。


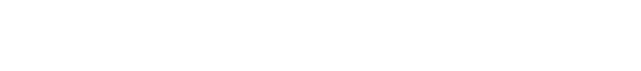
 弁護士
弁護士