山岳遭難救助事故を考える ~積丹岳遭難救助事件から~
1 はじめに(問題の所在)
山岳遭難事故では、これまではガイドや引率者の責任が問題とされてきたが、今回問題とされるのは遭難救助活動を行った行政(警察)の責任である。この問題については、「そもそも登山は自己責任であるから救助する側の責任を問うのはおかしい」とか、「救助する方も命がけでやっているのであり、その責任が問われるなら救助活動自体をやらなくなる」という救助する側の責任追求を否定する意見がある。果たしてそれは正しいのだろうか。今回は、2009年1月に北海道積丹岳で発生した遭難救助事故についての最高裁の判決が平成28年11月29日に出されたので、この事故を題材として検討してみたい。
2 積丹岳遭難救助事故の概要
遭難者Fさん(当時38歳)は、2009年1月31日スノーボードをするために友人二人と積丹岳(1255m)に登った。同日午後、友人二人とはぐれ、単独で山頂に向かったところ、天候が急変し山頂付近はホワイトアウトとなり、下山ルートを見失ったため、ビバーク(野営)することになった。
下山した友人から警察に救助要請がなされ、翌朝北海道警の山岳救助隊5名が捜索に向かい、正午頃ビバークしていたFさんを発見した。なお、FさんからGPSデータが警察に送られていたが、警察はデータを読み間違えていたため発見が2時間以上も遅れた。
救助隊員らは低体温症で意識朦朧となっていたFさんを抱えて下山し始めたが、進むべき方向を間違えて雪庇を踏み抜き200mほど滑落した。その後、救助隊員らは、Fさんをストレッチャー(そり)に収容し、急斜面を引き上げる作業に従事したが、途中でストレッチャーを持つ隊員を交代するため、ストレッチャーを1本のハイマツに紐で結んだ。その後、Fさんのザックを回収するため、救助隊員全員がストレッチャーから離れ誰もいなくなった直後、紐が外れてストレッチャーが斜面を滑落して見失ったため、Fさんの捜索救助を断念した。Fさんは、翌日崖下でストレッチャーに固定された状態で発見されたが、死亡(凍死)が確認された。
3 裁判の経過
本件は、警察の山岳救助隊の救助活動中に発生した死亡事故であり、遭難者Fさんの遺族が北海道警に対し、国賠法に基づく損害賠償請求訴訟を起こしたものである。
-
札幌地裁(平成24年11月19日判決-判例時報2172号77頁)
一審は、①北海道警の山岳における遭難者の救助活動は警察官の職務の一環として行われていることから、国賠法にいう「公権力の行使」に当たるとし、②山岳救助隊員として職務を行っている警察官が遭難者を発見した場合には適切に救助しなければならない職務上の義務を負うが、救助隊員の救助活動が違法と評価されるにためには、救助を行う際の救助隊員及び遭難者が置かれた具体的な状況に照らし、明らかに合理的と認められない方法をとったと認められることが必要であるとし、③最初にFさんを発見した場所のすぐ近くに雪庇があり、進行方向を間違えるとこれを踏み抜くおそれがあることを認識しながら、コンパスで位置を確認しながら進むという慎重な方法をとらなかったことから、進むべき方向を90度間違えて進んだため雪庇を踏み抜いて滑落した点に過失を認め、④他方でFさんの過失を8割と認定して、約1200万円の賠償を認めた。
-
札幌高裁(平成27年3月26日判決)
控訴審判決は、①警察による山岳遭難救助活動は、「個人の生命、身体及び財産の保護」(警察法2条1項)という警察の責務に含まれるとし、警察官の職務のとして北海道警の任務である山岳遭難救助活動を実施したのであるから公権力の行使に当たり、②救助隊員らは、警察官の職務として遭難者の捜索救助活動に当たっていたのであるから、遭難者を発見した時点で救助が不可能ないし著しく困難とは言えない場合は救助すべき職務上の義務(救助義務)を負っていたのであり、③救助隊員の救助活動が国賠法上違法となるのは、実際に救助活動に当たる救助隊員及び遭難者が置かれた具体的状況を踏まえて、合理的と認められない方法をとった場合に限られるが、④ずれ易い結び方(ひと回りふた結び)でストレッチャーをハイマツの枝(幹ではなく)に結束したこと、さらに救助隊員全員がストレッチャーのそばから離れたことに過失を認定し、⑤他方でFさんの過失を7割と認定して、約1800万円の賠償を認めた。
-
最高裁第三小法廷(平成28年11月29日決定)
最高裁は、北海道警の上告を棄却、上告審として受理しない決定を行い、これにより、北海道警の山岳救助隊員の過失を認め、北海道警に約1800万円の損害賠償を命じる札幌高裁の判決が確定した。
4 考察
-
本件は、民間のボランティア(例えば労山)による救助活動ではなく、警察(行政)が行う山岳救助活動の法的性格が問題とされた事件である。従来から山岳救助活動が国や自治体の責務かどうか曖昧であったが、警察の行う山岳救助活動が民間団体が行う救助活動と同じレベルの任意活動かどうかが問題となったのである。
-
警察による山岳救助活動の性格をどのように捉えるか。
これにつき、北海道警は、次のように主張した。山岳遭難救助活動は、山岳遭難救助の専門家が専らその専門技術及び知識経験を用いて行うものであり、元来は地元山岳会や大学山岳部の有志などの民間協力者によって実施されていたものであることから、北海道警の山岳救助隊による山岳遭難救助活動の性質は、民間救助隊の同種活動と異なるところはなく、権力的行政作用の性質はなく、北海道警の任務を達成するために必要な限度で行うことができる任意活動あるいは純然たる私的活動に準じるものであるから、国賠法1条1項所定の「公権力の行使」には該当しない。
しかし、警察による山岳救助活動が民間団体による救助活動と同様であるというのは明らかにおかしい。警察の責務は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じるものであるから(警察法2条1項)、警察官による山岳遭難者の救助活動は、警察官の職務の一環として行われていることは明らかである。従って、それは民間団体の救助活動とは質的に異なるものであり、国賠法にいう「公権力の行使」に当たるというべきであろう。
-
次に、山岳救助隊である警察官に救助義務があるのはいかなる場合か。
個人の生命、身体及び財産の保護に任じることは警察の責務であり(警察法2条1項)、また警察官は要保護者を発見したときは応急の保護をなすべきこと(警職法3条1項)に照らせば、山岳救助隊として職務を行っている警察官が遭難者を発見した場合には、適切な救助をしなければならない職務上の義務があるというべきであろう。
しかし、山岳遭難者の救助活動が警察の責務であるとしても、救助活動自体(特に冬山における救助活動)が救助隊員自身の身の危険を伴うものである以上、遭難者を発見したときはいかなる状況にあっても救助義務があるとまでは言えないであろう。遭難者の救助方法については、発見場所の状況、発見時の気象状況、救助に見込まれる時間、日没時刻、山岳遭難者の身体状態、救助隊員の人数・身体状態・携行する装備・応援の有無及び二次遭難のおそれといった種々の事情を考慮しなければならない。そして、これらの事情は刻々と容易に変わり得るものであるから、臨機応変に対応しなければならないが、救助隊員は登山及び遭難救助技術に当然習熟しているであろうから、遭難者を確実に保護するための適切な救助方法を決定するに当たっては、実際に救助活動に当たる救助隊員の合理的な判断に委ねるしかない。そうとすると、救助義務の有無は、救助を行う際の救助隊員及び遭難者が置かれた具体的状況に照らし、その時点において実際にとった方法が合理的な選択として相当であったといえるか否かという観点から判断されることになる。よって、救助隊員の救助活動が国賠法上違法と評価されるためには、救助を行う際の救助隊員及び遭難者が置かれた具体的状況に照らし、明らかに合理的と認められない方法をとったと認められる場合ということになろう。このような判断は、公務員の職務行為における過失は、当該公務員に対して職務上通常要求される注意義務に明らかに反すると見られるような不合理な行為であった場合に限り違法とされる職務行為基準説と同じであると思われる。
-
では、本件においては、具体的な救助義務違反があったといえるか。
-
ア 地裁判決は、救助隊員が遭難者を発見した場所から移動するに際し、進行方向を誤り、雪庇を踏み抜き200mほど滑落したが、滑落した斜面からストレッチャーに収容して引き上げに難航しているうちに再びストレッチャーごと滑落した結果、遭難者が凍死したことにつき、救助隊員らが当時の山岳訓練により発見場所の近くに崖があり雪庇を踏み抜く危険があることを認識しており、進行方向を誤れば滑落するおそれがあるにもかかわらず、常時GPSで位置を確認し、コンパスで方向を確認しながら進行するなどの慎重な方法をとるべき注意義務があったにもかかわらず、コンパスで数回確認したにすぎなかった点に過失を認めている。
これに対しては、低体温症の遭難者を発見して下山を急いでいる際に、現場において、判決が指摘するだけの余裕があるかどうか疑問であり、救助が困難な状況下において、下手すれば自分たちの生命も危険に曝すことになるのを顧みず救助活動をしている救助隊員にはいささか酷ではないかという指摘がある(長尾英彦・中京法学48巻3・4号255頁)。
-
イ 高裁判決は、地裁判決とは異なり、雪庇を踏み抜いて滑落した後の救助活動に救助隊員の過失を認定している。すなわち、滑落後、遭難者の引上作業を実施していた救助隊員らは、引上作業に当たる救助隊員が交代するまでの間、遭難者を縛着したストレッチャーをハイマツに結束するに当たっては、遭難者を滑落させないよう、結び目がほどけたり、枝から抜け落ちたりしないような結び方で結束するとともに、仮に結び目がほどけたり、枝から抜け落ちたりしても、直ちに滑落しないように予備的な措置を講じる義務があったとする。そして、①ハイマツはしなりやすいので、ロープを結ぶときは根元に結束しなければならないが、それをせず枝に結んだこと、②さらに結ぶ方法も山では一般的にとられている、引っ張れば引っ張るほど輪が締まる方法(例えばブルージック、オートブロックあるいはクレムハイスト)ではなく、引っ張っても輪自体は締まらない「ひと回りふた結び」という方法であったこと(「ひと回りふた結び」の方法で枝に結んだため、結び目の輪が枝の先の方にすべり、しなった枝から抜け落ちてしまった)、③また救助隊員の誰か一人でもストレッチャーの側についていれば落ちそうになったときにすぐに確保できたのに、全員がストレッチャーから離れてしまったことが具体的な過失の内容であるとしている。つまり、ハイマツへの結束方法およびストレッチャーのそばから離れたことの2点に過失を認定したのである。
-
ウ 検討
過失の捉え方については、地裁判決より高裁判決の方が理に適っていると思われる。なぜなら、雪庇を踏み抜いて滑落した後も、救助隊員らは遭難者を確保して引上作業に従事することができ、例え急斜面だったとしても、引上自体が不可能な状態ではなかったからである。疲労の見える隊員の交代時において、山岳救助の訓練を受けた救助隊員であるならば当然行うべき方法をとらなかったことに過失を見出しているのは妥当な結論と思われる。
-
-
終わりに
山岳地帯を抱える長野県警や富山県警等の山岳救助隊は日常的に救助訓練を行っていることで有名であるが、北海道警の山岳救助隊はどうやらそうではなさそうである。GPSデータを読み間違えたり、進行方向を90度も間違えたり、ロープの結束方法も知らなかった。おまけに急斜面で遭難者を収容したストレッチャーの側を全員が離れるという過ちまで犯している。山を知らず、まともな救助訓練も受けていないと言われても仕方がない「救助」活動だったと言える。
山岳遭難事故は、自ら危険な自体を招いたという点で世間から非難されることが多いが、その後の救助活動におけるミスについてまでも自招したわけではない。もちろん、遭難者の落ち度については、裁判所も厳しく見ており、地裁判決は8割、高裁判決は7割も過失相殺をしている。
本件事故は、警察(行政)の救助活動の責任を問うたものであり、民間人によるボランティアによる救助活動とは異なる。救助活動に従事する隊員の職務上の注意義務が問題とされているからである。警察や消防などが救助隊を組織して救助活動を行う場合には、救助隊としての救助技術や経験を積んでいることが前提となっていると思われる。登山ブームで山に登る人が激増している現在、山岳救助の方法や山岳救助隊のあり方(遭難者を発見してヘリで運ぶというだけの方法は問題である)が問われており、今回の判決は警察による山岳救助隊の質的な充実を求めるものと受け取るべきであろう。
このような山岳遭難事故が起こる度に、「自己責任」論が噴出し、登山に対して規制をかけるべきだという論調が跋扈するようになることを危惧する。もちろん、登山には大なり小なりリスクがつきものであり、登山者自身が山を知り、山を学ぶという謙虚な姿勢が必要なことは言うまでもない。
-
追記(富士山救助ミス事件)
2013年(平成25年)12月1日富士山の御殿場ルートの9.5合目付近で男女4人が滑落するという事故が発生したが、当時静岡県の防災ヘリは定期点検中で出動できず、応援協定に基づき、静岡市消防航空隊のヘリが救助に向かった。その救助活動中に、ヘリで男性1名を吊り上げて収容しようとしたところ、吊り上げ用具が外れて3mの高さから落下させ、その後滑落して行方不明になった。翌日男性は発見されたが、死亡が確認されたという事故が起こっている。この事故を巡っては、遺族が静岡市を被告として京都地裁に損害賠償請求訴訟を提起している(第1民事部係属)。救助の際には、航空隊員が一度男性をヘリに収容しかけたものの、足の一部がスキッド(ヘリの着陸脚)に引っかかったことに気付かず、吊り上げ用具を引っ張って男性を地上に落下させてしまったとされる。この裁判においても、行政(静岡市)の救助義務違反があったかどうかが問われているが、一旦遭難者に装着して吊り上げた救助用具が外れたのであるから、救助用具の装着に不十分な点があったことは否定できないよう思われる。


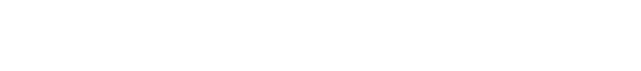
 弁護士
弁護士